訪問診療をしていると時々患者さんやご家族に「お家にいながら入院していると思って下さい。」とご説明することがあります。これは簡潔に言うと、家で在宅療養しながらも、あたかも病院にいるのと同じような医療が提供される、ということです。このような考え方・医療提供モデルを英語でHospitalization At Home (HAHやAHAと略されます) などと言うことがあります。Hospitalizationは英語で「入院する」という意味なのでまさに「家で入院する」という言葉です。具体的に説明していきます。
まず、あなたが病院で入院しているとイメージしてみて下さい。
・・・・・・
あなたはベッドに横になっていますが、右脇腹が少し痛い気がしてきました。でも今見ているテレビも面白いし、もう少し様子を見てみるか、とテレビを見ていると、どんどん右脇腹が痛くなってきます。あーこれはもう我慢できないなーとなってきたらあなたはどうしますか?多くの方はベッド脇についてるボタン(ナースコール)を押して看護師さんを呼ぶのではないでしょうか。看護師さんがベッドに来てくれて「〇〇さん、どうしました?」と聞いてくれます。「看護師さん、なんだか右脇腹が痛くなってきました。」とお話すると熱を測ったり血圧を測ったりして、お腹を触ってくれました。その後「先生に連絡しますね。」と言ってくれて、なにやらお医者さんに電話してくれているようです。「先生からカロナールを飲ませるようにと指示が出たので、カロナールを飲みましょうか」と看護師さんは説明し、カロナールという痛み止めを持ってきてくれました。薬を飲んだところ15分くらいで痛みは治まってきて、また落ち着いてテレビが見られそうです。
・・・・・・・
こんな入院生活があるかもしれません。では、家ではどうでしょうか?・・・
・・・・・・
あなたはベッドに横になっていますが、右脇腹が少し痛い気がしてきました。でも今見ているテレビも面白いし、もう少し様子を見てみるか、とテレビを見ていると、どんどん右脇腹が痛くなってきます。あーこれはもう我慢できないなーとなってきたらあなたはどうしますか?訪問看護を契約していたので、訪問看護師さんにまずは電話で相談してみました。電話で話すと訪問看護師が心配してくれて、30分くらいかかりましたが訪問看護師さんが部屋に来てくれて「〇〇さん、痛みはどうですか?」と聞いてくれます。「看護師さん、まだ右脇腹が痛いままです。」とお話すると熱を測ったり血圧を測ったりして、お腹を触ってくれました。その後「先生に連絡しますね。」と言ってくれて、なにやらお医者さんに電話してくれているようです。「先生からカロナールを飲ませるようにと指示が出たので、カロナールを飲みましょうか」と看護師さんは説明し、カロナールという痛み止めを持ってきてくれました。薬を飲んだところ15分くらいで痛みは治まってきて、また落ち着いてテレビが見られそうです。
・・・・・・
これがまさに「家で入院する」一例です。病院にいるのとほぼ変わりない対応・処置を受けることができました。住み慣れた大好きな家で病院と同じような医療を受けて過ごすことができたら、とても良いと思いませんか?この後訪問診療を受けていればお医者さんに直接診察に来てもらうことができますし、状況によってはもう直接訪問診療の先生に来てもらってスピーディーに対応してもらうこともできるかもしれません。
訪問診療をしていると患者さんや家族から「熱が出たらどうしたらいいですか?熱というのはそもそも何度ですか?カロナールを1回飲んだら次は何時間後に飲めるのですか?食事をしていなかったらどうしますか?」などなど質問攻めにあうことがあります。そんな心配性な患者さんやご家族には「ここは病棟で入院していると思ってみて下さい」と上記のようなお話をします。「何かわからなかったら、ナースコールみたいに訪問看護か訪問診療に直接電話していただいて良いんですよ」とお伝えすると、とても安心していただけることが多いです。薬の内服や坐薬の投与、点滴の確認など、ともするとご家族にとっては不安でいっぱいになる対応をしなければならなくなる状況では、このような「家で入院している」ような医療提供体制の確保が必須だと思われます。
ここで「家で入院する(Hospitalization At Home)」ことのメリットをまとめてみたいと思います。
【「家で入院する」メリット】
- 住み慣れた家で過ごせる。家族やペットに囲まれて過ごすことができる。
- 家族が一緒に治療方針や病状説明に立ち会うことができ、方針決定も一緒にしていくことができる。
- 費用的には入院するより安くなることが多い(場合によります)。
上記「2. 家族が一緒に治療方針や病状説明に立ち会うことができ、方針決定も一緒にしていくことができる。」についてはかなり大きなメリットかと考えています。病院に入院している患者さんに面会に行ったことのある方であれば経験があるかもしれませんが、患者さんにいつの間にか新しい点滴が繋がっていたり、いつの間にかベッドの場所が移動していたり、下手をするといつの間にか具合がとても良くなったり/悪くなったりしていたり・・・ということがあると思います。病院の先生もなかなか病状や治療の状況をその場にいない家族や関係者に連絡・相談していくという時間や余裕も取れないですし、逆に迅速な対応のためには説明などは後回しにせざるを得ないかと思います。一方在宅医療では、基本的には患者さんの他にもご家族などが一緒にいらっしゃる場合が多いので、ご家族にも「これから~~の点滴をしますね」や「血圧が低めなので〇〇の薬を減量しましょう」などの病状説明・治療方針説明が必然的にされやすくなります。病状についても「熱が出ているのは〇〇の感染があるからですね」や「食事量が増えてきたのは〇〇の病勢が薬の効果で落ち着いてきたからだと思います」など、訪問診療の医師や訪問看護師などのさりげない一言でグッと理解しやすくなることがあると思います。一緒に家族(患者)の病状を理解し、一緒に治療方針を決定していく、ということができるのは在宅医療の非常に大きなメリットであると考えています。
「家で入院する」のメリットばかり書いてきましたが、ではデメリットはないでしょうか。正直なところ当然あります。まとめてみます。
【「家で入院する」デメリット】
- 家で病院と同じ医療を受けられる、と言いつつもやっぱり病院よりは制限がかかることはある
- ナースコールはすぐに出来るが訪問看護師や訪問診療の医師の訪問には病院よりはタイムラグが生じる
1.については、大学病院を始めとする急性期病院にもともと勤務していた私の視点ではやはり自宅での医療に限界があるのは事実です。例えば重症の感染症を起こした時に血液の細菌培養検査(血液培養・血培などと言われます)をして、検出された細菌に応じて様々な抗生物質(抗菌薬)で治療したりすることはなかなか在宅では「完璧には」難しいです。なぜなら一部の抗生物質は1日4回投与しなければならなかったり(メロペネムといういわゆる「最強」の抗生物質など)、あまり使われることがないため珍しい抗生物質(リネゾリドなどの「マニアック」な抗生物質が例に挙げられます)は用意自体していない在宅クリニックが多かったりするためです(クリニックにより「どこまでのことが家でできるか」は異なるので確認が必要です)。
2.については患者さんの家とクリニックや訪問看護ステーションとの距離などにもよりますが、やはりタイムラグは生じてしまいますので注意は必要です。ただ病院であってもその時の病棟看護師さんの手の空き具合や先生の都合などにより直接見てもらえるタイミングは様々なので、必ずしも病院にいる方がすぐにいつでも会いに来てもらえる、というわけではないことも留意しておきましょう。「家で入院する」場合には看護師さんや医師がどれくらいの時間で来てくれるのか、最も急げばどれくらいで遅ければどれくらいなのか(重症度に応じた訪問時間)を確認しておくと安心できると思います。
「家で入院する」ことについて御紹介してみました。患者さんの家の状況、家の場所、近くのクリニックの状況・マンパワーなどにより話が変わりますので、是非患者さんはご自身の最寄りのケアマネジャーさんやクリニック・訪問看護ステーションなどにご相談してみて下さい。
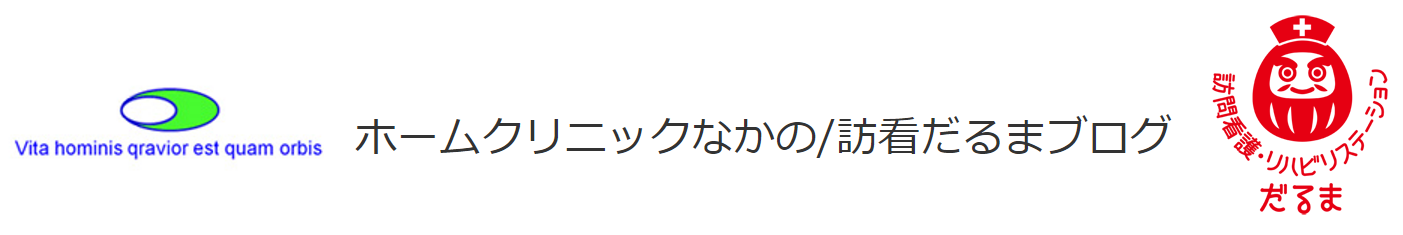
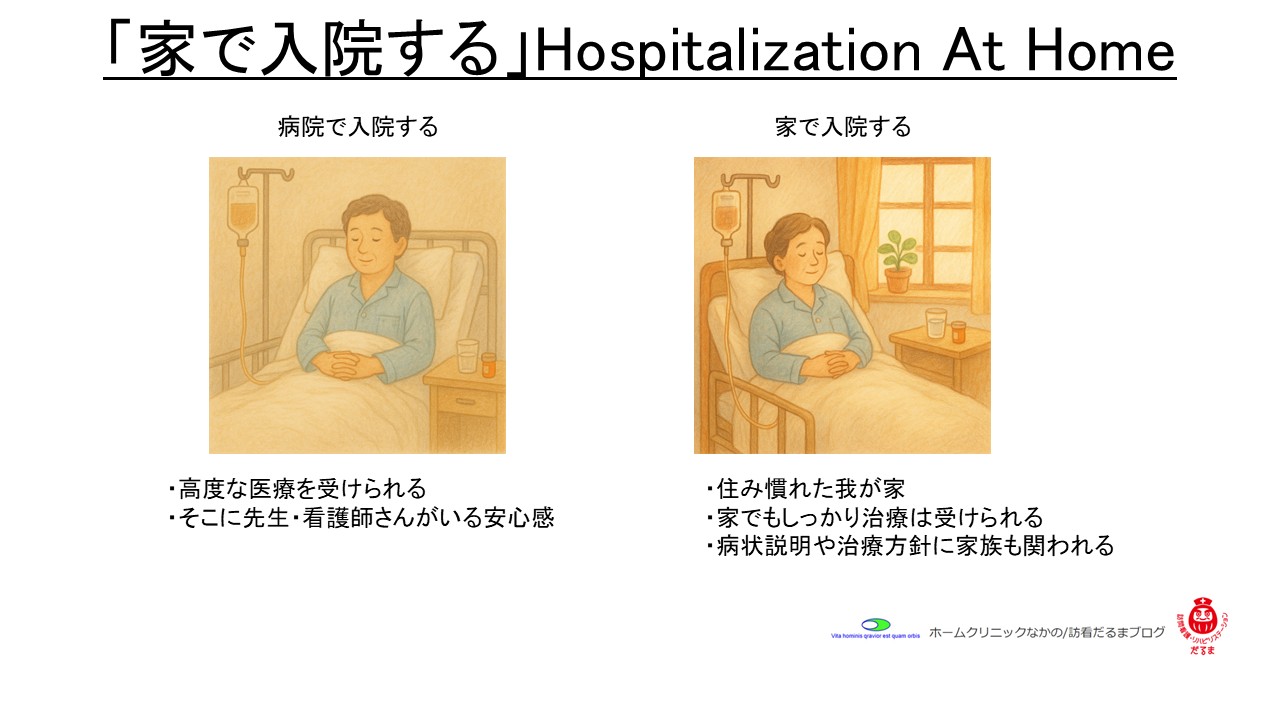


コメント